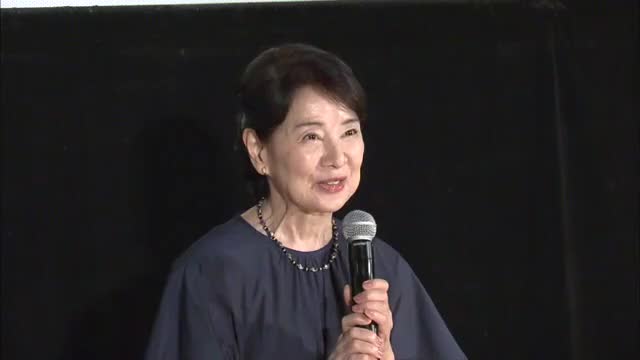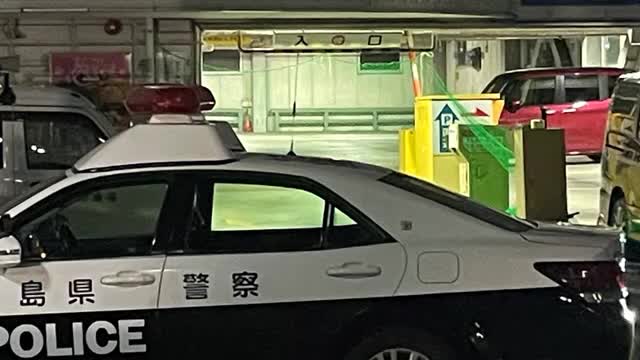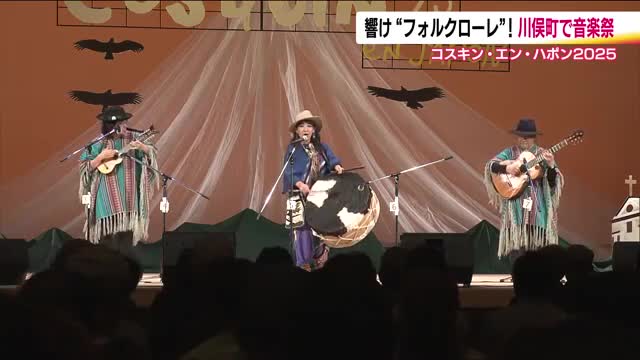今はなき地域のシンボル「原町無線塔」を後世に 解体から40年以上 展示を通して思い出と共に振り返る
かつての福島県南相馬市を写した写真のなかで、存在感を放つ高さ201メートルの「原町無線塔」。昭和57年に老朽化によって取り壊されるまで、まちのシンボルとして親しまれてきたこの塔を、市民の思い出とともに振り返る催しが開かれた。(~10月13日まで)
■故郷のランドマーク
「あの塔が見えたら近くに家があるっていう、故郷のランドマークだったってこともありますし、実は日本の無線通信のなかで大きな役割を果たした」と話すのは南相馬市博物館の二上文彦館長。
1981年、解体が進む原町無線塔の映像。外に取り付けられたエレベーターをのぼると、まさに無線塔の目線、南相馬市を一望できる景色が広がっていた。。
■わずか10年で役目を終える
「原町無線塔」は、1921年に運用を開始したアメリカとの無線通信のための電波の送信塔。土木技術を結集して建てられたこの塔は、当時、エッフェル塔に次いで世界で2番目の高さを誇り、関東大震災の第一報をアメリカに伝えるなど大きな役割を果たした。
しかし、無線技術のめまぐるしい進歩で時代に遅れをとり、わずか10年ほどでその役目を終えた。
■ふるさとの誇りは心の中で
アマチュア写真家として無線塔を撮影し続けた大槻明生(おおつき あきょう)さん、91歳。解体から40年あまりが経ち、無線塔が輝いていた当時を知る世代が少なくなったことに少し寂しさを感じている。
「無線塔知らない人にもこういう展示を見てもらって、これが我が町にもあったということを、若い人に引き継いでいきたいと思います」と大槻さんはいう。
ふるさとの誇り「原町無線塔」は、これからも市民の心の中で生き続ける。