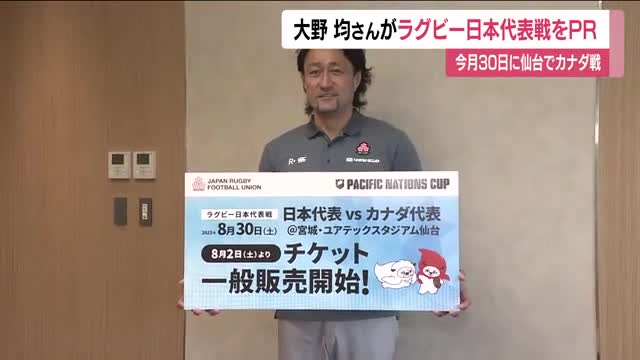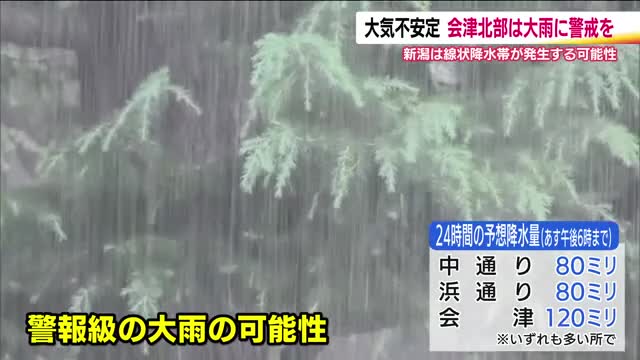福島第一・燃料デブリ本格取出し工程案 経産相「重要な前進」評価も収益改善を指示

東京電力の小林喜光会長や小早川智明社長は8月5日に武藤容治経済産業相と面会。福島第一原発3号機での燃料デブリの本格的な取出しに向けた工程案を示し、武藤経産相は「重要な前進」と評価した。
3号機での本格的な取出しをめぐっては、東京電力が7月に工程案を原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)に示し、一定の技術的な成立性が確認されている。
「気中での取出し」「一部の燃料デブリは充填剤で固めてそれごと取り出す」という工法で、格納容器の"横"と"上"からそれぞれ燃料デブリにアクセスする計画。放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要があり、東京電力は「準備に12~15年かかる」としている。これによって大規模取出しの開始は2037年度以降とされ、これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」の達成は極めて困難な状況となった。
東京電力の小林会長は面会で「まさに前人未踏の領域に進むという極めて困難な取り組みに挑戦しなければならない、改めて身の引き締まる思い」とし、小早川社長は「準備工程の期間・費用が見通せるところまで廃炉が進捗したものと受け止めている」「廃炉等積立金制度に基づき、前年度(2024年度)末までに7,122億円の積立金を確保していて、当面の資金確保に支障はないと判断している」などとした。
武藤経産相は「燃料デブリの取り出しに向けた準備工程について技術的成立性が確認されたことは、今後安全かつ着実に廃炉を進めていくうえで重要な前進」としたうえで、東京電力に対し「今後、取出しを本格化するにあたっては更なる困難も予想され、これまで以上に持続的で、安定的な資金の確保が欠かせない」などとして収益改善も求めた。
東京電力ホールディングスが公表した2025年度第1四半期(4~6月)の連結決算では、燃料デブリの本格的な取出しの準備に向けた費用として9,030億円を計上し、この期間としては過去最大の8,576億円の赤字に転落している。
廃炉全体にかかる費用は約8兆円と見込まれているが、廃炉作業の全体像はまだ見えていない。
面会終了後、東京電力の小林会長と小早川社長は報道陣の取材に応え、経営の安定化の重要性などについて強調した(以下は回答の一部抜粋)。
Q 第1四半期の連結決算で巨額赤字を出したことへの受け止めと財務状況改善に向けた方針は?
A(小早川社長)廃炉として様々な部分が見えてきたというのは一歩前進だと思っている。そのうえで必要な資金はしっかりと認識してそれに対して対応していく。足元のキャッシュフロー等が厳しい状況にあることは大臣にお伝えしている通りだが、投資の厳選やグループの聖域なき合理化などを私の陣頭指揮の下で進めている。福島への責任をまっとうすると同時に、我々のもう一つ大きな柱である電気の安定供給をしっかり実現していく。
Q 新増設など原子力をめぐる動きについて
A(小早川社長)資源の少ない我が国にとっては原子力エネルギーの活用は非常に重要だが、安全と地元のご理解があってのことと考えている。
A(小林会長)日本の経済を考えるとエネルギーはますます重要になっていく。世界に取り残されない、AIが進化して時代が音を立てて変わっている中で、世界から来てもらうためにはエネルギー不足だけは避けたいと考えると、おのずと基本的な方向性は決まってくるのではないかと思う。
Q 廃炉費用を8兆円と見積もっていたが不足の可能性は?
A(小早川社長)当社が見積もったものではないため、妥当性を申し上げる立場にはないが、この金額に基づいて廃炉の積立金制度が進められている。廃炉の全体像はまだ分からないが、その枠内の中で一部の部分がクリアになったと認識している。今の範囲をしっかりこなしていくことが大事だと考えている。
Q 第一原発で掲げている「2051年廃炉完了」見直し必要性は?
A(小早川社長)今回は全体の枠組みとして、ロードマップの改訂はせずにこのなかでおさまっている。(2051年の廃炉完了は)福島の復興をなし遂げるために定めた、地元の期待も背負った大きな目標なので、我々に与えられた責務として何とか実現するように頑張ってまいりたい。