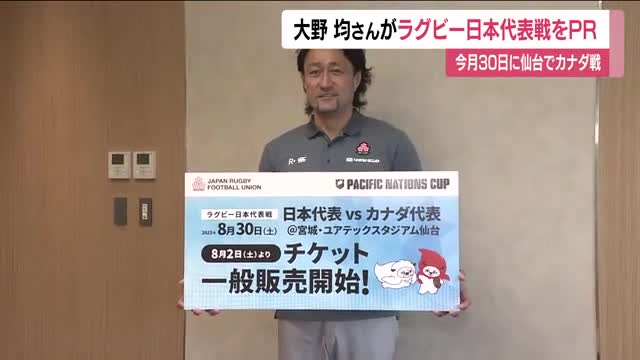燃料デブリ本格取出し 東電「この1、2年で内部調査の準備・実施」<福島第一原発>

東京電力は8月7日、福島県が設置する「廃炉安全監視協議会」で、福島第一原子力発電所3号機での燃料デブリの本格的な取出しに向けた工程案などを県や自治体、有識者に説明し、参加者からは安全対策や廃棄物の削減についての明確な方針を示すよう声が上がった。また「県民に対して直近の詳細な工程を示すべき」との意見に対し、東京電力は「ここ1、2年では、現場の放射線量低減などの環境改善や、内部調査の準備・実施を行う」とした。
福島第一原発の廃炉をめぐっては、東京電力が7月に、3号機での燃料デブリの本格的な取出しについて、「準備に12~15年かかる」との方針を示した。燃料デブリの一部を充填剤で覆ったうえで、格納容器の"横"と"上"からそれぞれアクセスし気中で取り出す計画だが、放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要があり、本格的な取出しの開始は2037年度以降と計画される。
これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」の達成は極めて困難な状況となっているが、廃炉完了の目標として掲げている「2051年」を現時点で見直すことはないという。
また、東京電力ホールディングスの2025年度第1四半期の連結決算では、本格的な取出しの開始に向けた準備のための費用として9,030億円を計上し、この期間としては過去最大となる8,576億円の赤字に転落した。
8月7日の「廃炉安全監視協議会」では作業の安全面について「上からのアクセスの際に原子炉圧力容器の上部構造物はどうするのか」という意見が出された。東京電力が「小さな穴を複数あける計画」とすると、別の委員からは「放射性物質の飛散の対策を十分に取るように」などといった声が上がった。
また、「デブリに水をかけながら作業を行うということは汚染水が大量に発生することにならないか」といった意見に対し、東京電力は「原子炉を循環させる水で対応する」と説明。発生する廃棄物への対応については「まとまり次第改めて説明する」としている。
また、「12~15年かかる」とされている準備工程案について委員から「大まかなくくりになっているが県民のためにここ数年で何を計画しているのかを示すべき」との意見が出された。東京電力は、詳細については今後「廃炉中長期実行プラン」のなかで公表するとしたうえで、「ここ1、2年では、現場の放射線量低減などの環境改善や、内部調査の準備・実施を行う」とした。
福島第一原発では "廃炉の最難関"と呼ばれる燃料デブリへのアクセスに向けた検討が進められている。
2024年11月、事故後13年8か月が経過してようやく、2号機で初の「試験的取出し」に成功。約0.7gの採取デブリからは核燃料の主成分であるウランの含有などが確認され、2025年4月には、2回目の取り出しで約0.2gの採取に成功している。
一方、福島第一原発に残る燃料デブリは1号機に279t、2号機に237t、3号機に364tの計880tと推計されている。2回の採取量を合わせても、残るデブリの10億分の1程度と、取り出し完了までの道は遠い。
2011年の事故で、2号機は水素爆発を起こしておらず1・3号機と比べて損傷が少ないとされることから先行的に試験的取り出しが行われているが、事故から14年が経過してまだ2回目。
3号機では大規模取出しに向けた工程案が示されたばかり。1号機ではプールからの核燃料取出しのために建屋を覆うカバーの設置工事が進行中で、燃料デブリの取り出しについても内部調査が継続されている段階である。