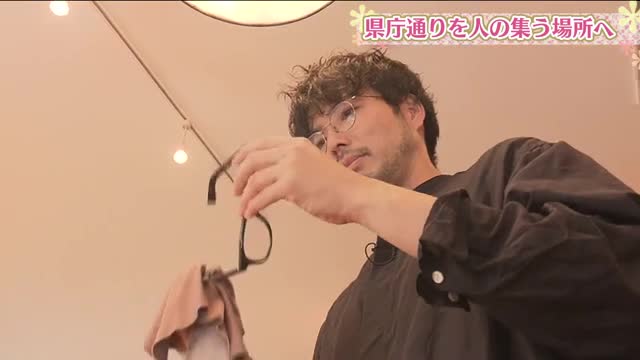"2051年"廃炉達成は可能か NDF「現時点で目標を変える必要はないと思っている」<福島第一原発>
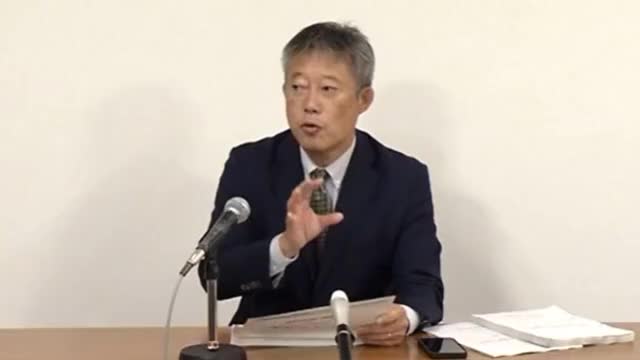
福島第一原子力発電所の廃炉をめぐり、技術的な観点からの助言や指導などを行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は10月30日に「廃炉のための技術戦略プラン2025」を公表した。
前年から一部のリスクの見直しなどを行ったものの、NDFは「中長期ロードマップの改訂を求めるものではない」として、"2051年までの廃炉完了"の実現可能性を否定しなかった。
NDFは毎年、福島第一原発の廃炉に向けて課題を抽出し、技術的な見解を示したうえで翌年度の東京電力予算に反映させるための「技術戦略プラン」を作成している。
10月30日に公表された今年の戦略プランは、7月に東京電力から示された「3号機での燃料デブリの本格的な取出しの工程案」を踏まえた内容となった。
3号機の燃料デブリ取出しは「気中での取出し」「一部の燃料デブリは充填剤で固めてそれごと取り出す」という工法で、格納容器の"横"と"上"からそれぞれ燃料デブリにアクセスする計画となっていて、これまでNDFは一定の技術的な成立性を確認している。
この工程案をめぐっては、放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要があり「準備に12~15年かかる」見通し。これにより大規模取出しの開始は2037年度以降とされ、これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」の達成は極めて困難な状況となった。
福島第一原発では、国の廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で決定される「中長期ロードマップ」に基づいて廃炉作業を進めているが、このなかで廃炉の完了は事故から30~40年後の「2041~2051年」とされている。国と東京電力が掲げるこの「2051年廃炉完了」について、NDFは「2051年が難しいと思えばきちんと政府に提言をすると思うが、技術専門家の集団として、技術的な根拠をもって提言する材料は現時点で揃っていない」などとした。
一方、2051年までの廃炉をめぐってはNDFの更田豊志 廃炉総括監(元原子力規制委員会委員長)が2025年5月20日に福島県福島市で開かれた報道記者との懇談会で「個人的な見解」としたうえで、「2051年にデブリの取り出しが完了しているはずがない」と発言。「中長期ロードマップの見直しはあり得るのか」という質問に対し、「見直しはあり得るどころか必須」と回答した経緯もある。
廃炉に向けての "最難関"とされる燃料デブリの取り出しにも大きな課題がある。
福島第一原発では、事故後13年8か月が経過した2024年11月にようやく、2号機で初めてとなる燃料デブリの採取に成功。その後、2025年4月に2回目の採取を実施した。
第一原発に残る燃料デブリは1号機に279t、2号機に237t、3号機に364tの計880tと推計されているが、2回の採取量を合わせても、残るデブリの10億分の1程度と、取り出し完了までの道は遠い。
2号機の試験的取り出しでは、格納容器につながる配管の中に、事故の熱で溶けたケーブルなどが固まって詰まっていたため、2回の採取とも、比較的狭い場所を通ることができる"釣り竿型"のロボットを使用。
一方で、78億円をかけて製作した大型の"ロボットアーム"は一部のケーブルが経年劣化で断線していたことが発覚。また、搭載するカメラの耐放射線性がメーカーの仕様を満たさず交換が必要になったとして、「2025年度後半」としていた次回のデブリ採取を「2026年度着手」と延期した。
NDFはこの問題についても「ショックだったしびっくりした」としたうえで「安定的にカメラの性能を確保していかないと長期的な廃炉に影響を及ぼす」と、廃炉作業におけるカメラの重要性を強調した。
福島第一原発の廃炉の完了は2051年と掲げられている。
国・東京電力・NDFともに、現時点でこの目標を変える見通しは示していないほか、「最終的な廃炉の絵姿」についても明確な言及はない。