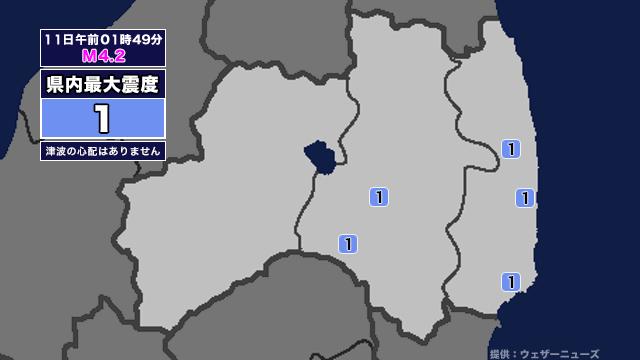【東日本大震災から14年半】福島"復興の現在地"は?

2011年3月11日に発生した東日本大震災から14年半が過ぎた。
福島県によると、県内の死者は4,180人で、このうち2,349人が震災関連死。また、23,987人が今なお避難生活を送っている。(いずれも2025年8月1日現在の状況)。
国は2026年度からの5年間を「第3期復興・創生期間」と位置づけ、全体の事業規模を1.9兆円程度とする基本方針を閣議決定している。このうちの大部分、1.6兆円程度が福島県にあてられ、廃炉や住民の帰還の推進のために2025年度までの5年間を約5,000億円上回る額となっている。
<残る"避難指示">
福島第一原子力発電所事故後に福島県内の面積の約12%に出された避難指示は、除染やインフラの整備により解除が進み、約2.2%にまで減少した。
立ち入りが制限される帰還困難区域の中には、帰還意向のある住民が帰還できるよう国費で除染やインフラ整備を進める「特定帰還居住区域」が設けられている。現在、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市、葛尾村の6市町村に設定されていて、このうち浪江町では帰還に向けて特例的に宿泊を認める"準備宿泊"を2025年7月から開始している。
<進む復興と回復>
福島県内での、東日本大震災の災害復旧工事は全体の99.9%が完了している。
また、避難指示が出された地域周辺の復興や住民の帰還を加速させるため8路線を「ふくしま復興再生道路」と位置付けて整備を進めるなど、災害に強い県土づくりが進められている。2025年8月にはこのうち自動車専用道路である「小名浜道路」が開通した。
福島県産食品の輸入を規制している国や地域は、震災当初の55から6にまで減少し、2024年度の県産農産物の輸出量は前年度の約2倍で約898tとなり、過去最高となった。
一方、震災後に大幅に落ち込んだ県産農産物の価格は回復傾向にあるものの、全国との価格差がいまだ回復していない品目もある。福島県が取りまとめた「復興・再生のあゆみ」によると、2024年時点でモモは1kgあたり117円差、和牛は1kgあたり218円差、2023年産のコメは60kgあたり437円差となっている。
被災地における営農再開も進み、2024年度末時点での営農再開率は50%を超えた。
事故直後に操業自粛を余儀なくされた県内の沿岸漁業は、魚の種類や漁の回数を制限しながらの「試験操業」を2021年に終了。現在は本格操業に向けた移行期間となっていて、2024年の水揚量は震災前の約4分の1となっている。
福島県は震災後、補助金などで企業立地を支援している。県全体の製造品出荷額等は、震災前の水準を超えるまでに回復している一方、双葉郡では震災前の4分の1程度にとどまり、市町村ごとに復興の度合いに濃淡があるのも現実となっている。
<福島第一原発の廃炉>
福島第一原発では、国の廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で決定される「中長期ロードマップ」に基づいて廃炉作業を進めているが、このなかで廃炉の完了は事故から30~40年後の「2041~2051年」とされている。国と東京電力は現状でこの「2051年の廃炉」を変更はしていない。
福島第一原発では、事故後13年8か月が経過した2024年11月にようやく、2号機で初めてとなる燃料デブリの採取に成功。その後、2025年4月に2回目の採取を実施した。一方、福島第一原発に残る燃料デブリは1号機に279t、2号機に237t、3号機に364tの計880tと推計されていて、2回の採取量を合わせても、残るデブリの10億分の1程度と、取り出し完了までの道は遠い。
また、2025年7月には、燃料デブリの3号機での本格的な取出しに向け、東京電力が「気中での取出し」「一部の燃料デブリは充填剤で固めてそれごと取り出す」という工法で格納容器の"横"と"上"からそれぞれ燃料デブリにアクセスする工程案を示した。放射性物質の飛散防止などのために設備や建屋を増設する必要があり、大規模取出しの開始は2037年度以降とされていて、これまで掲げられていた目標である「2030年代初頭の着手」の達成は極めて困難な状況となった。
東京電力ホールディングスが公表した2025年度第一四半期(4~6月)の連結決算では、燃料デブリの本格的な取出しの準備に向けた費用として9,030億円を計上し、この期間としては過去最大の8,576億円の赤字に転落している。
廃炉にかかる費用は約8兆円と見込まれているが、廃炉作業の全体像はまだ見えていない。
<"除染土"の行方>
原発事故後に県内の除染で出た土は双葉町と大熊町にまたがる「中間貯蔵施設」に運び込まれている。2025年8月末時点で、中間貯蔵施設に搬入された除染土は約1,413万立方メートルで東京ドーム約11個分に相当する。
1kgあたり8,000ベクレルを超える、放射能濃度の高いものについては、熱処理などで量を減らしたうえで「県外最終処分」する方針。これは中間貯蔵施設に保管されている除染土の約4分の1にあたる。法律(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法)において「中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが国の責務として明記されているため、2045年3月までの県外最終処分実現が"約束"となっている。
2025年8月26日に開かれた閣僚会議では、福島県外最終処分の実現に向けて"今後5年程度"の政府の取り組みを整理した工程表が示された。2030年度ごろから候補地の選定や調査を開始し、2035年を目途に候補地を選定、その後、用地取得や処分場の建設などを実施し、2045年3月までの最終処分を実現する計画としている。
一方、残りの大部分を占める放射能濃度の比較的低いものについては「公共工事などでの再生利用」の方針で福島県内での実証事業も進められているが、新宿御苑の花壇や埼玉県所沢市の芝生広場で利用する計画は、近隣住民の理解が得られず進んでいない。2025年7月、トラック1台分に相当する除染土が首相官邸に運び込まれ、初の「再生利用」の事例となったが、大規模な再生利用の受け入れ先はまだ決まっていないのが現状となっている。
東日本大震災から14年半。
復興と再生をより強力に進めていくことが求められている。