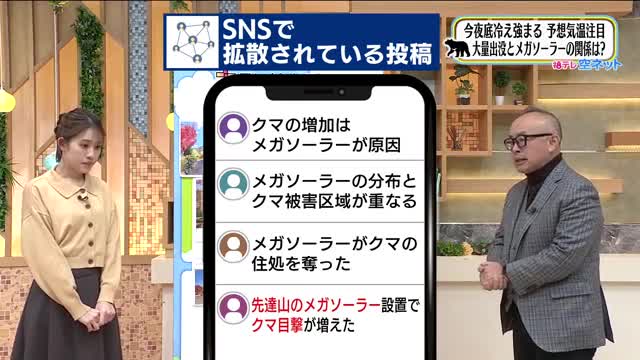「迎えに行くだけなのに進まない」JR郡山駅前ロータリーの大混雑 一極集中が背景に...社会実験で解決へ
「迎えに行くだけなのに、なかなか進まない...」JR郡山駅前の西口ロータリーでは、そんな声が日常になっている。こうしたなか、慢性的な混雑の原因を探り、改善していこうと郡山市が新たな一手を打った。渋滞は解消できるのか?市民にとって身近な"駅前の未来"を模索している。
■青信号でも進めないほどの混雑
2025年11月10日から郡山駅前の西口ロータリーで始まった「交通社会実験」。駅前で以前から問題になっているのが『混雑』。夕方の送迎や新幹線発着の時間帯になると車が溢れ、青信号でもロータリーに入っていけないほどの渋滞が起きる。
利用者からは「娘の迎えで良く使う。混雑時は前が進まないので、ずっと待っている状態」「タクシーの乗り入れもあるので、その辺の兼ね合いが上手くいけばいい」との声が聞かれる。
■混雑解消へ社会実験
郡山市では、タクシーの待機レーンの一部に6台分の臨時の乗り降り場を設置。また、それでも混雑している場合は、近くの市営駐車場の屋上も開放し、混雑解消のためにどの程度の乗り降り場を確保すればよいか、検証を行う。
郡山市建設構想部・道路保全課の相樂寿和さんは「乗降場設置の効果や、乗降場の駅からの距離と利用率の関係性などを確認したい。今後の郡山駅西口ロータリー改修や駅周辺全体の基本構想の策定に反映したい」と話す。
この社会実験は、駅前が特に混み合う午後4時から午後9時まで実施され、東口も含めて3カ所(11月10日~23日西口ロータリー・11月10日~23日市営駐車場・11月17日~30日東口周辺の市道)に臨時の乗り降り場が設けられる。
■一極集中 郡山駅の特徴
交通政策に詳しい福島大学経済経営学類の吉田樹教授は、駅前の渋滞は車への依存度が高い地方都市ならある程度起こり得るとした一方で、郡山駅特有の事情も指摘した。
吉田教授は「郡山駅の場合は、新幹線が止まる駅であるということと、それ以外の大きな駅がかなり離れている。一極集中的に郡山駅に乗降が集中することが特徴」と話す。
また「郡山駅には、通勤通学や観光、さらに首都圏などから仕事で訪れる人も多く、一極集中となって他の駅に分散しないのが混雑の大きな原因」と説明する。
■動線を分けてスムーズな循環を
今後、混雑緩和に向けてのポイントとなるのが『動線』の分離だという。
吉田教授は「タクシーと一般車の動線を変える・分離するということは、構造上としてやっていかなければいけないこと」と話し、タクシーと一般車両、さらに比較的長く停車する迎えの車を分けることで、スムーズな循環を促す必要があるという。
また駅の近くに駐車場を整備するなど、ロータリーに入る車の絶対量を減らす施策も併せて行わなければ、根本的な解決にはならないと指摘した。
郡山市では、複数の改修案を検討していて、今回の社会実験の結果などをもとに2027年度中にロータリーの改修工事を行う計画だ。