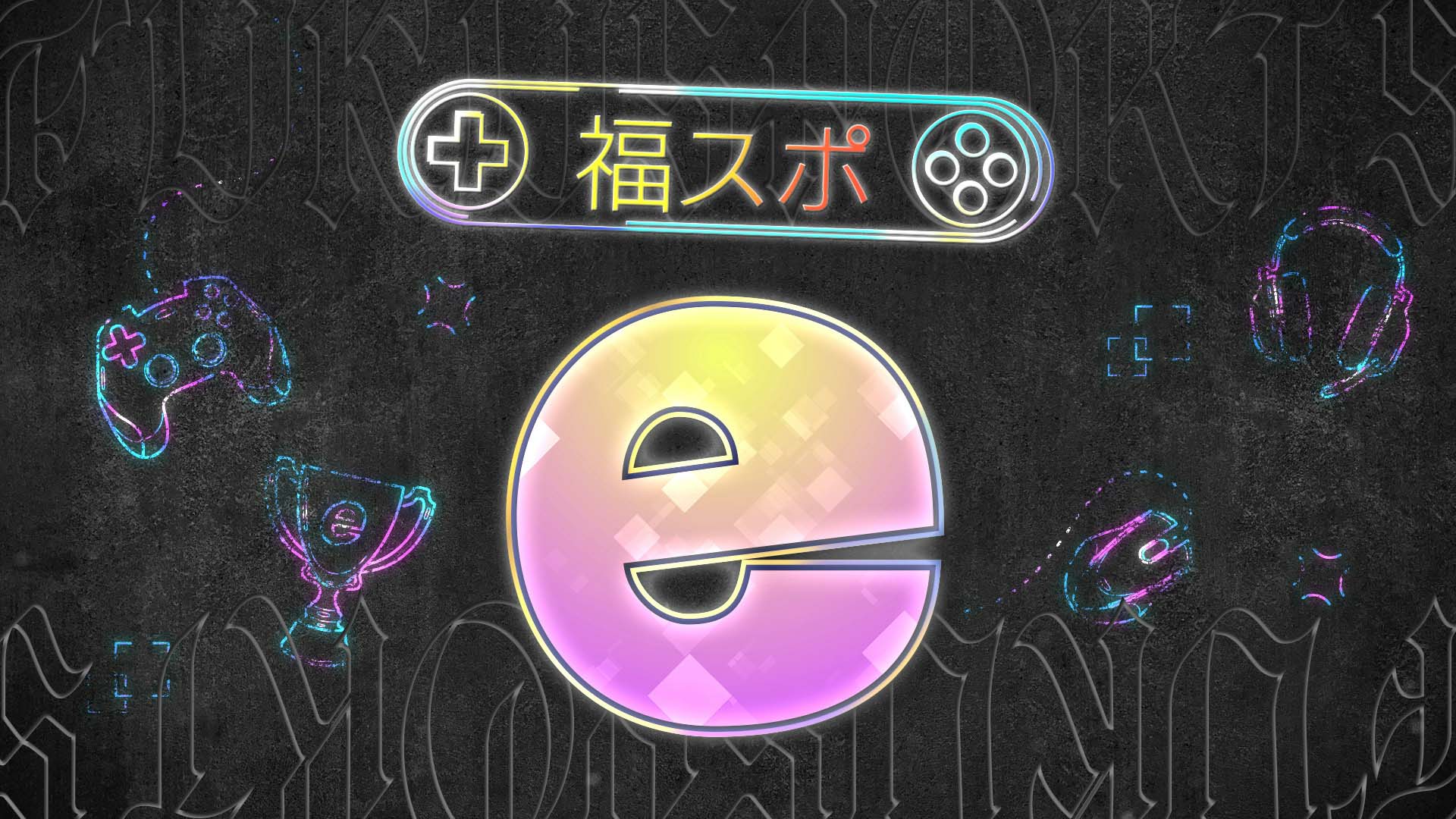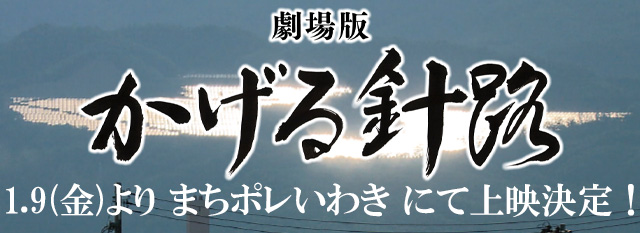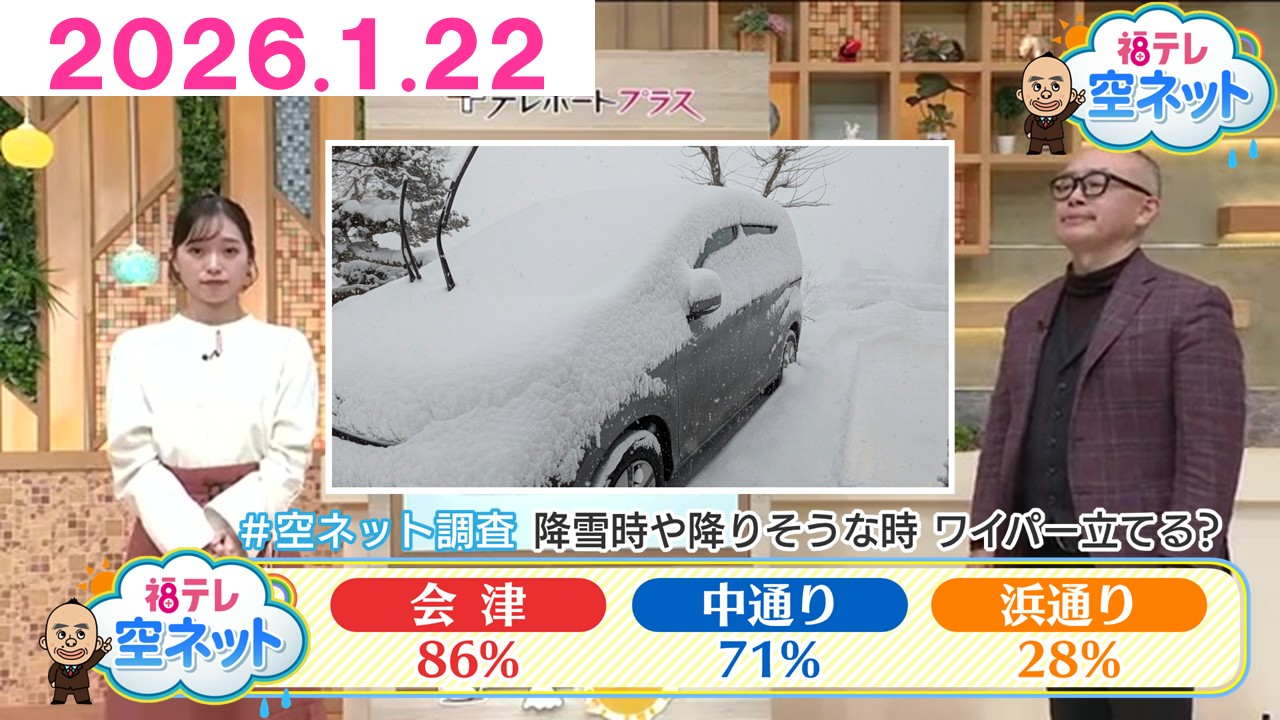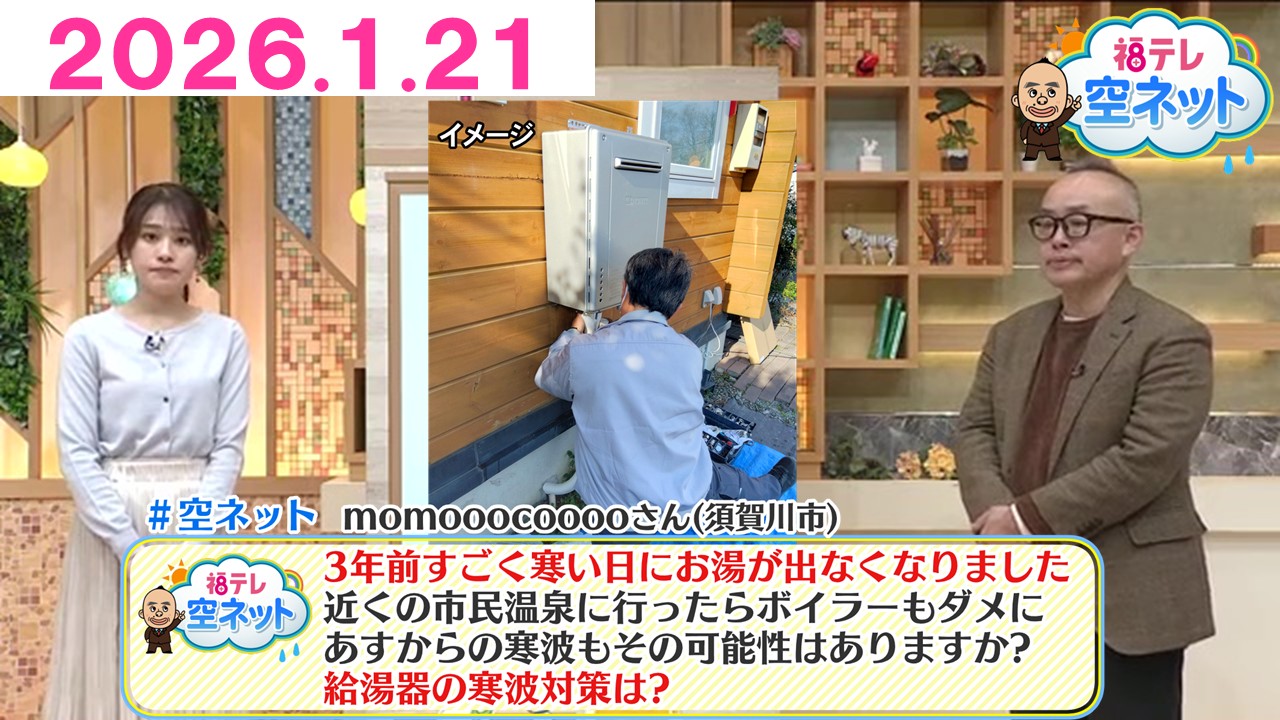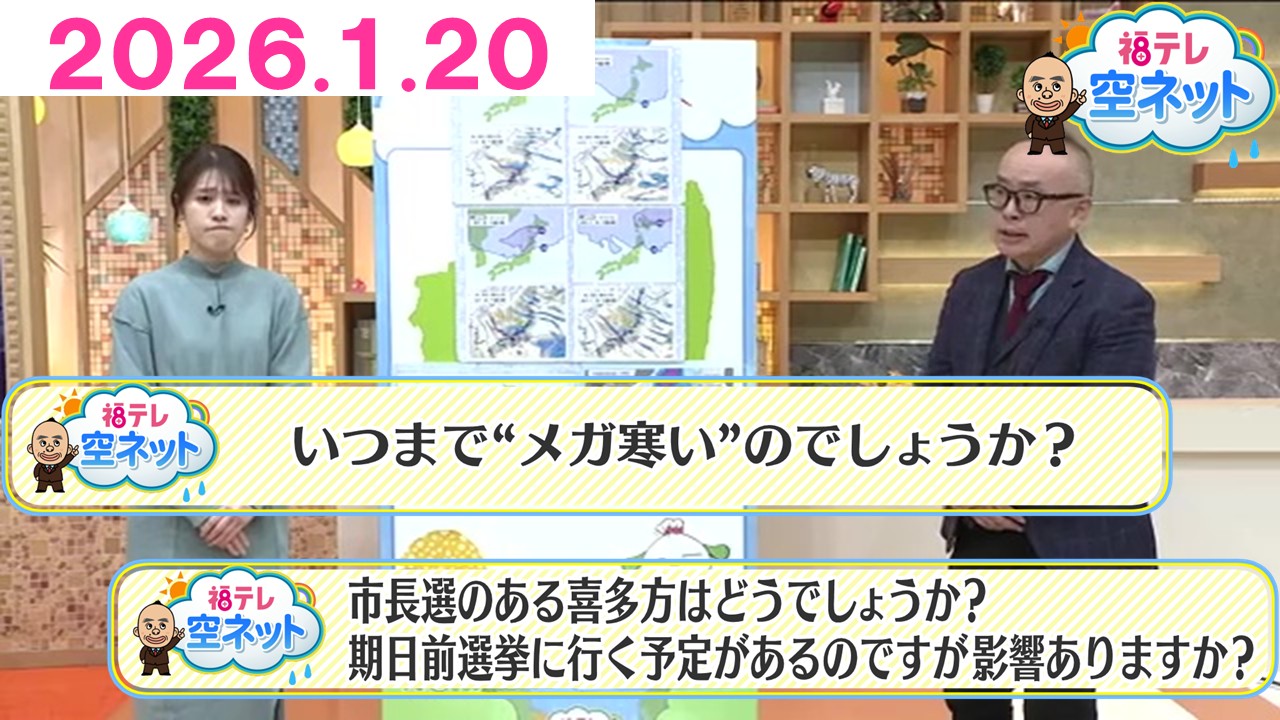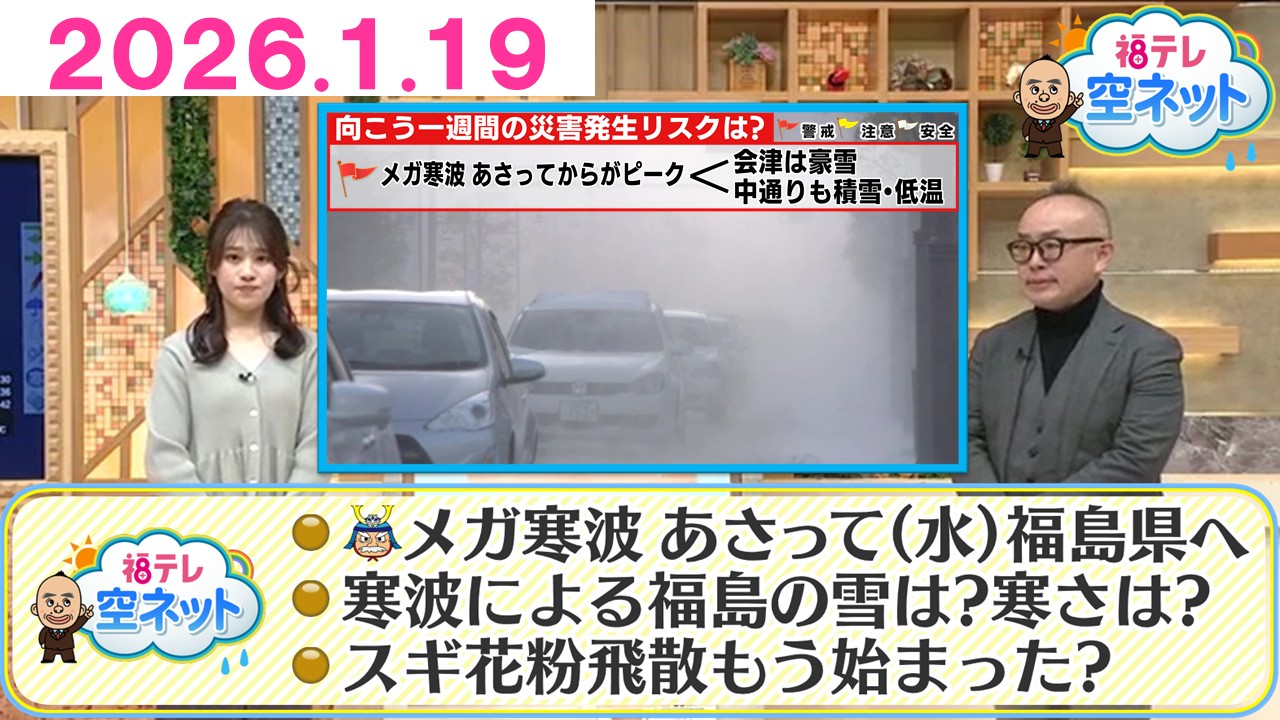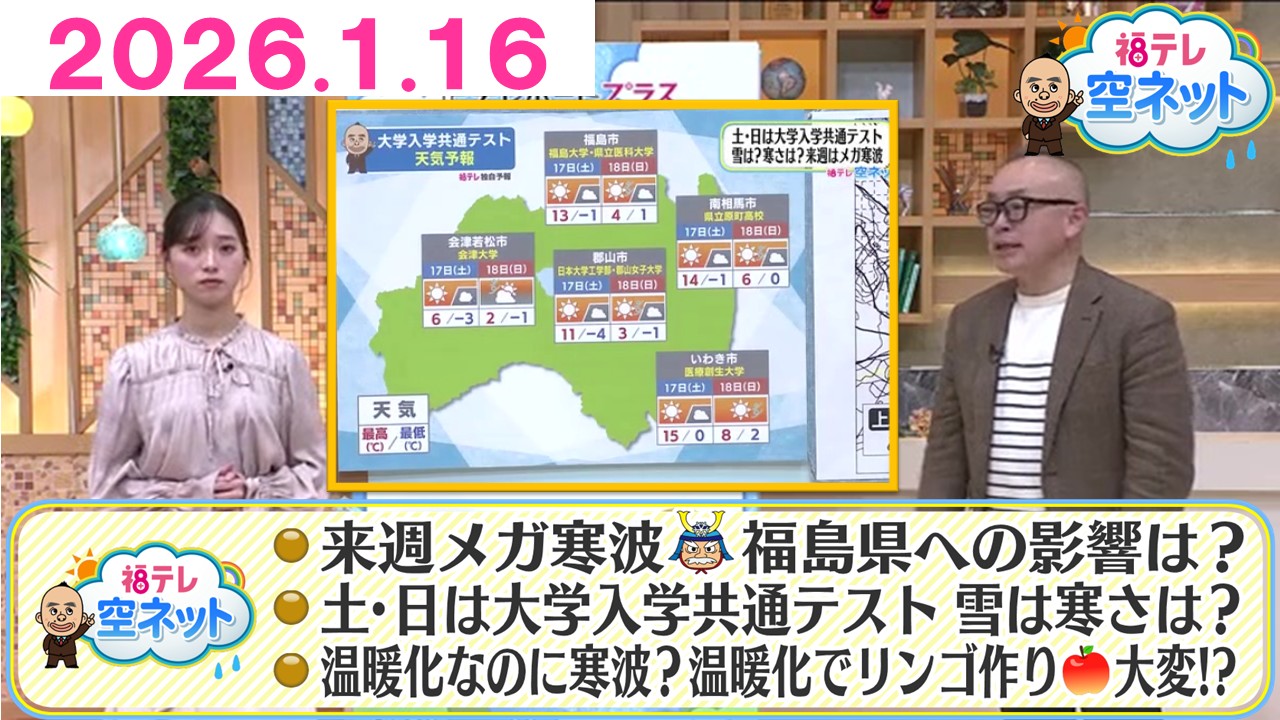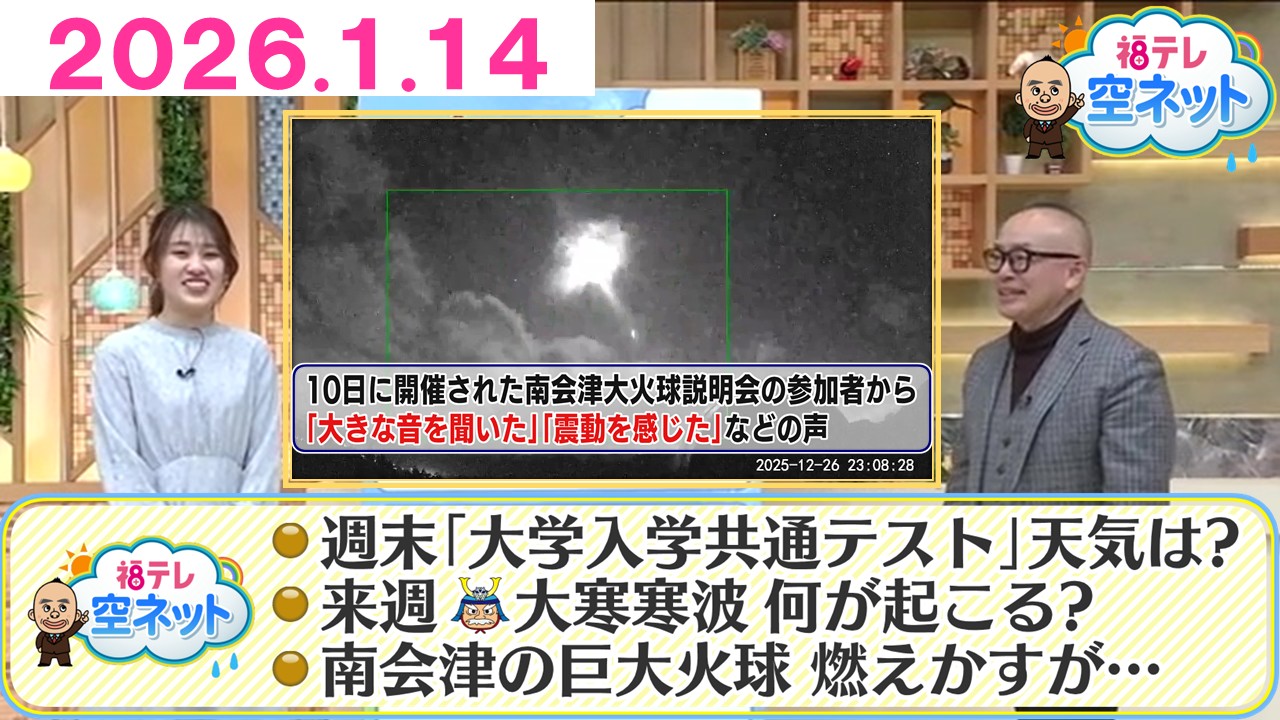テレビ番組テレポートプラス
素材の声を聞く料理人・平山真吾 原発事故後の福島で挑む新たな食の哲学『命を語るひと皿』

私たちが口にする食材の数だけ命がある。福島の大地を自ら歩き、命と出会う一人の料理人。提供する一皿で"命の物語"を届ける。
◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます
理想を形にするための閉店
料理人・平山真吾は、順調だった店にあえて終止符を打った。
「寂しさというよりかは、期待しかない。マイナスイメージでお店をたたむわけじゃないので」と話す。
平山は、数年前から山や森に入り食材を集め始めた。「実際こういうところに、こういうのが生えていると自分も体験しながら、それをお客さんに伝えられたら、すごく良いのではないかと思って」と理由を語る。

意識を変えた出会い
山の案内役を担うのが天然食材ハンターの小豆畑浩稔(あずはたひろとし)。希少な食材がとれる場所を自分の足で見つけてきた小豆畑は、本来、決して他人の同行は許さない。
平山だけは特別だ。「お店も改装して土地も買って、天然食材に全部振り切って、どれだけの時間とお金を使ったかっていうのは、想像できるので」と小豆畑はいう。
春山に芽吹く山菜の数々は、一般的に使われないクセの強い食材も多い。
小豆畑との出会いが平山を変えた。レストランを一度閉め、理想とする料理を模索し始めた理由の一つだ。
平山は「自然の香りとかを嗅いだ時に『これ使えそうだな』とか、景色だったりとか土だったり、自然界に触れていると料理のイメージが湧いてくる」という。
平山の新たな料理は、レシピ帳や厨房からは始まらない。一皿の始まりは、その手のひらにある。

命と向き合う料理人
命をとるだけではなく、育てることも平山の料理の一部。放棄された畑に手を加え、ブルーベリーを収穫している。
「大変なのですよ。地味だけど、一切薬とかもかけてないから虫も食べちゃうし、鳥も食べるし」と平山はいう。
厨房では気づけない食材にかかる手間や苦労。獲る命も、育てる命もある。すべてを一皿の上で頂く。それが新しい料理の理想形...のはずだった。
福島には、どうしても皿に乗せられない命がある。
「生きるのに必死なわけですから、それは残酷。残酷というよりかは、ただただ殺すっていうのは悲しい」と話す平山。
原発事故後、福島の野生動物は出荷制限・摂取制限がかけられた。(※現在では一部制限が緩和)未だにこの土地には、命を奪っても料理に出来ないものがある規制の中で、ただ静かに消えていく命が。この矛盾と向き合うことが平山の覚悟だ。

頂いた命に新たな意義
新しい料理を表現するため、必要だった店の再構築。
福島県内で初めてのジビエの加工施設も整備する。平山は「今まで野菜や米、海産物が解除になっていくなかで、ジビエだけが解除になっていなかった。1つの足がかりになるのではないかと期待しています」と話す。
理想を形に変えたレストラン「四季彩 平山」。最もこだわるのが"火"。「素材に対しての火入れっていうのは、本当に生かすか殺すかになってしまう」という。以前は手の込んだ調理や複雑なソースが自慢だった。今は、それ以上に素材の声を聞く。
『食材をいかす』それは奪った命にもう一度意味を与えること。
「自然界から少しだけ、僕らが食べる分だけおすそ分けして頂いた命を、その生命力をうちでまたさらに食べて頂く人の生命力の返還してもらえればいいかなっていう考えで、いま料理しています」と平山はいう。

おいしさの先にあるもの
平山は、自ら食材を集め自然での体験を伝える。皿の向こう側にある命の物語を。
森で手にした命も、畑で育てた果実も、語られずにただ消えていく命さえも、平山はすべてを受け止め皿に乗せる。
「普段、普通の方が絶対立ち入らないようなとこに入っているので、そういう背景を思い浮かべながら食べていただくことで、より一層おいしさと命をいただくっていうことの実感がすごく伝わるのではないかと思います」と平山は話す。
届けるのはただの『おいしさ』ではない。自然の豊かさ命と向き合う日々、そして福島という土地が抱える現実。平山の皿が語り掛けている。